お知らせ
11.Dec.2020
DISCOVER JAPAN
お坊さんも走るんです

12月は「師走(しわす)」とも言います。お正月を控えて一番忙しい一年の最後、やることが多いので本当にずっと走りまわっているようなイメージです。実は、日本には昔から年末になるとお坊さんに自宅まで来てもらい、お経を唱えてもらう風習がありました。そのため、年末が近付くとあちこちから依頼がくるお坊さんは、東西を行ったり来たりと大忙しになります。その様子を見て「師が馳せる」から師走になったという説もあります。
12月になると、こんなにたくさんやることがあります。
- クリスマスの飾り付け、準備(クリスマスツリーや食事、プレゼント等)
- 年末年始の帰省などの手配
- お正月の準備
- 年賀状の準備
- 大掃除
- 冬至(とうじ)
- お歳暮:日頃からお世話になった人に対し感謝を込めて品物を贈る行為
みなさんも今年「嬉しかったこと」「できたこと」「良くなったこと」などを振り返ってみましょう。年末に一年のまとめをして、今後はどうあるべきかを考えてみましょう。その時にはネガティブな考えばかりするのではなく、ポジティヴな考え方をして、年末にしっかりと振り返りをするようして、来年の目標を立てましょう。
すすはらい
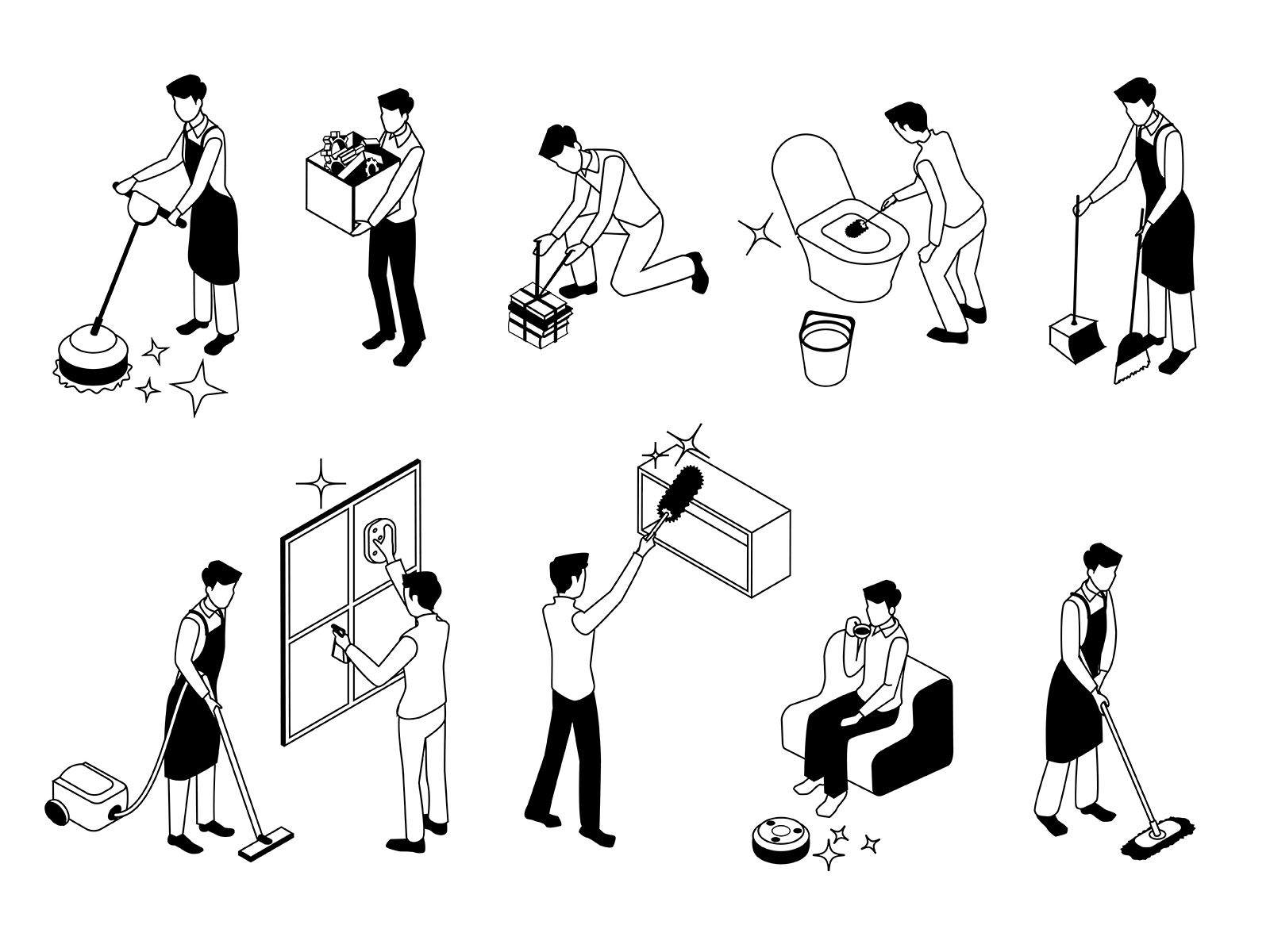
正月を迎えるため、1年間にたまったほこりを払う日が「煤払い(すすはらい)」といいます。昔は、かまどや灯台で火を使ったので部屋に「すす」がたまりました。正月の神さまをお迎えするため、清らかな場所になるようにと、日ごろあまりしないところもきれいに大掃除をします。
また、日本神話には、けがれを祓うことで清らかな新しい命が生まれるという「死と再生」の考え方が見られます。一年の終わりに大掃除を行うことは、その年に付いた厄(やく)やけがれを掃除して払い、新しい年を迎えるという考え方につながったのかもしれません。
一般家庭では、年末の大掃除として家族全員がそろいやすい12月26日ごろから行うところが多いようです。みなさんも自分の部屋だけではなく、いつも使っているリビングルームや台所を掃除して、気持ちよく新年を向かえるために、力を合わせて、家をピカピカにしましょう!!!

